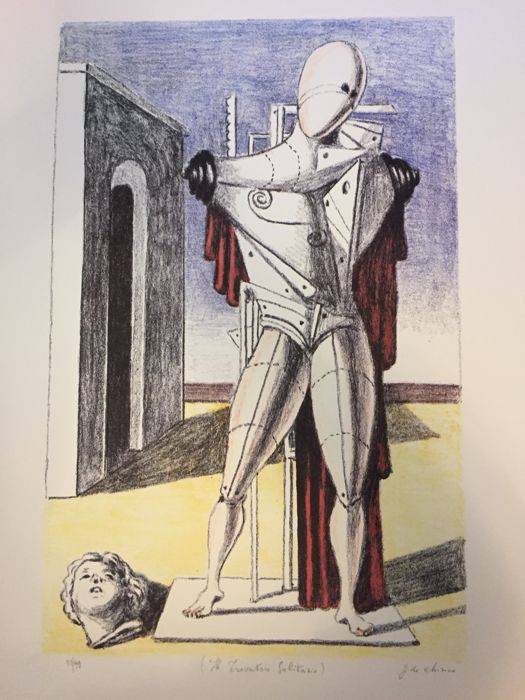2月7日金曜日付『東京新聞』夕刊文化面に、藤田一人という美術評論家の書いた文章が載っている。興味を引かれたので、以下に一部省略して引用する
見出しは「今様の展示に昔を思う」
◇
古い映画のこんなワンシーンが心に残っている。平日の美術館、一人の男が旅行者らしい女性に声を掛けて怪訝な顔をされる。すると男は「昼間から美術館にいるのは失業者か変人と相場が決まっているから」と自虐的な一言。今では問題発言かもしれないが、美術館のイメージを絶妙に物語る。そこから浮かび上がるのは、往年の絵画や彫刻が淡々と並ぶ時が止まったような空間。そこにいると社会の束縛からほんの一時、解放されたような気持ちになり、ただただ時間を過ごせる。
しかし、そんな美術館のイメージは、今は昔。近年ではさまざまに工夫を凝らし、観客を楽しませる。今や美術館は有意義な時間を過ごす場所なのだ。東京でも長年屈指のコレクションを誇ってきたブリヂストン美術館が、建て替えによる4年半の休館を経てこの1月にアーティゾン美術館として再スタート。名称とともにその展示や運営の変貌ぶりには今日の美術館のあり様を印象付けられる。
象徴的なのが、入場券の日時指定予約制。事前にウェブ予約をしなければならない。その際、学生以下は無料。ただ、余裕があれば当日券も発売されるが割高で、学生割引もない。混雑を解消する目的だというが、情報化時代の合理的かつ機能的な管理方法だ。また、入り口ではセキュリティー対策の持ち物検査も。
まさに時代の趨勢といえる。
そして展示空間が2倍になり、凝った演出も目を引く。開催中の開館記念展は、同館のコレクションを、従来の時代や地域、分野別ではなく、時空を超えた美術作品の出会いや関係性を物語る。
(略)
既存のイメージを払拭し、これまでにない作品の見方を通して、新鮮な美術鑑賞を提起しようとする。このようなキュレーションは、昨今の美術館では盛んに試みられている。ただ、こうした展示が延々と続くと、ここまで饒舌に語られなければいけないのか?と、食傷気味にもなってくる。
すると、かつてのブリヂストン美術館を思い出す。初めて上京した時に、ふと訪れた平日の人けのない常設展示で、教科書に載っているモネやセザンヌの本物を見た驚き。また仕事の合間に入った折に、青木繁の『海の幸』を初めて見たこと。
時代遅れの男の愚痴かもしれないが、昨今の美術館は少々息苦しい。
(下線Takeo)
◇
美術館を訪れなくなって久しい。3年ほど前に、一度、渋谷のBunkamuraに連れて行ってもらった。それが、約6~7年ぶりの展覧会であった。それ以降も美術館には足を運んでいないし、これからももう美術館を訪れることはないだろう。
上に書いたように、今の美術館の様子をまるで知らない。それにわたしは、美術館で、作品をスマホで撮影している人がいるような場所には行きたくないのだ。
上記の記事に書かれているように、今は美術館は、「ただただ時間を過ごせる」場所ではなく、「有意義な時間を過ごす場所」になっているようだ。それにいったい「アーティゾン美術館」とはなんだ?随分と厳めしい名前を付けたものだ。「アーティゾン」とは何語で、どういう意味があるのだろう?
日本人の欧米拝跪はとどまらない。昨年は、ここから駅までの道に「北欧住宅」が建ち、先ごろ同じ道筋に「カーサ・〇〇」という「アパート」が出来た。わずか200メートルほどの道に北欧と南欧が同居している。(' Casa 'とはスペイン語で' ハウス' の意味だ)
◇
藤田氏の書いていることが、全ての美術館に当てはまるわけではないだろうが、トウキョウの美術館事情が、このような流れになっているということは確かだろう、この先「持ち物検査」を実施する美術館も増えることだろう。
普通の人たちにとって、この「趨勢」が、美術館、そして「アート」への敷居を低くしているのか、或いはその逆なのか?また、「今の人たち」が美術館という場所に何を求めているのか、わたしにはわからない。けれどもわたしにとっては頻繁に美術館に通っていたことも、既に「今は昔の物語り」である・・・
[関連投稿] 「公共空間」について、鉛筆の芯と、さくらの花びらの危険性について