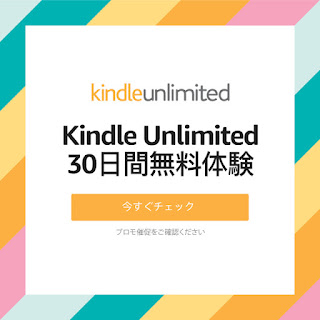先日以下のような文章をネット上で見かけた。
書かれていたのは、社会を批判をする前に、「自分自身の社会性の欠如」を省みるべきではないか、といった主旨の文章であった。文中、わたしの記憶に強く残っているのは、
「社会批判の前に、自らが社会性を備えれば、批判の対象がなくなるかもしれないから。」
この文章を書いた者にとって「いま・ここに在る(社会の)現実」は、個々の実存、「個々人の抱える現実」に優先される。
「社会を批判する前に、先ず自分自身の『社会性』の欠如に目を向けろ」と。
これは容易に「いじめる側」の論理に通じ、そして「いじめられる側にも責任はある」と言った戯言(たわごと)に極めて近似した、残忍で冷酷な考え方であることがわかる。
では「社会性」とは何か?簡単に言ってしまえば、自己を取り巻く有形無形の環境への適応能力であり、順応性の謂いである。己を取り巻く「現実」への順応性・適応性が高い者ほど、「自分」=「エゴ」というものの弱さが目立つ。自身のスタイル、ポリシー、美意識、価値観、譲れない拘りなどがなく、自己の内面の水位と、社会の水位が常に平衡を保っている者ほど、社会性は高く、独自性は希薄である。
◇
Anniston, Alabama, 1936, Peter Sekaer (1901 - 1934)
ナチの支配する「社会」があり、軍国主義が国民全体を洗脳する「社会」もまた「いま・ここにある社会」である。彼の理屈を極限まで推し進めれば、「プロテスト」というものは必然的に否定される。
「レジスタンス」「パルチザン」も、「ゼネスト」も「百万単位のデモンストレーション」も「暴徒化」も、なべて「社会性の欠如」に因があるということになるのだろう。
この写真の若者たちも「有色人種専用階段」の存在=「差別の象徴」を批判する前に、自分たちの「社会性の欠如」を省みた方がいいようだ。
◇
North Carolina, (Segregation Fountain), 1950, Elliott Erwitt
「ノース・キャロライナ 白人と有色人種とに分けられている水飲み場」1950年
写真 エリオット・アーウィット
「いかに多種多様な個別性を包摂し得るかがその社会の成熟度の指標である・・・」などと、高校の優等生の言うような「陳腐な」セリフを今更言う代わりに、わたしは以下のセリフを引用する。
*
“ Let my country die for me.”
― James Joyce, Ulysses
「この国をわがために滅ぼしめよ」
ー ジェームス・ジョイス 『ユリシーズ』
ー追記ー
「社会性を備える」と言うことは、換言すれば、「わたし」が「わたし」であることを、「自己のアイデンティティー」を放棄せよということと同義である。何故なら「社会」(=多数派)と「私」(個ー「絶対的マイノリティー」)とは常に対立関係にあるものだから。