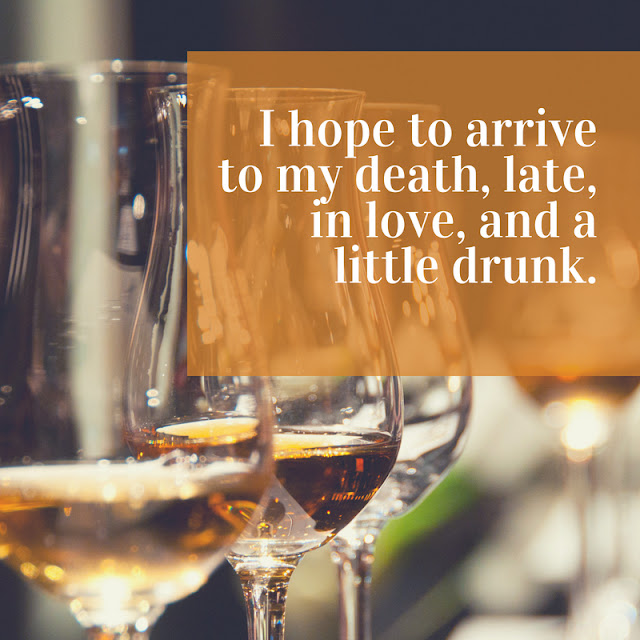● わたしはあまりに永く生きすぎたようだ。40代の後半、当時のSNSの友達に、
50歳になったら自殺すると言っていて、まだのめのめと生き永らえている。
その間にそのSNSの仲間が4人死んだ。イタリアの男性(50代)と女性(30代)、スペインの女性(40代)、アメリカの女性(40代)・・・みなやさしいいい人たちばかりだった。
55歳、永く生きすぎじゃないか・・・
● 今80歳で重い持病を持つ母といのちを共にすることは、決して変わることのない気持ちだ。仮に母亡き後に数億の財産があったとしても、わたしの気持ちは何も変わらない。
この世に生まれてきて、唯一わたしに親切にしてくれた人、その存在なくしてはただの一日も生きることはできない。
つまりもうあまり長く生きなくてもいいということだ。
● 心を病んだ人たちのブログを読むと、わたしなどよりも遥かに重い症状に苦しみながら、何らかの形で「社会復帰」を成し遂げたいと考えている人が多いことに驚く。
35歳の時、つまり20年前に社会から完全にリタイアして以降、わたしは社会への復帰ということを一度も考えたことがない。母も、その間関わった何人かの精神科医も、現在の主治医も、一言も「社会復帰」などと口にしたこともない。決して「やさしい」とは言えない生活保護担当のケースワーカーでさえ、「作業所?はは、あんたのような根気のない人に単純作業が勤まるわけがないでしょう」と一笑に附した。
わたしに勤まる仕事はないと皆わかってくれていることは助かっている。
● もう本を読めなくなって何カ月にもなるし、観たい映画=ビデオを借りることもままならなくなった。わたしを取り巻く世界はわたしの意思に関わりなく日毎に収縮してゆく。
わたしが外に出たくても、出させない。
昔のように簡単にはビデオ(DVD)を廉価では借りさせない。
● 最近フォローしたブログの筆者の文才に嫉妬する。
彼の読者が口々に言うように、何故彼はものを書く仕事を探さないのだろう?
何度も書いているように、過去に小規模ながら「出版社」に籍を置いて、三度が三度とも「キミはモノを書く仕事には向いていない」と、僅か数カ月で馘になった経験のあるわたしのような者には、彼の巧まざる文才が妬ましい。というよりも、何か一つでも秀でた才を持つ者が、Good For Nothing =いいとこナシのわたしには、単純に羨ましいのだ。
まぁだからこそ、辛い勤めをしなくてすんでいるのだが・・・
「塞翁が馬」。極端に劣っているということも、まんざら悪いことばかりではないということか・・・
孤独中年男の細々生活記